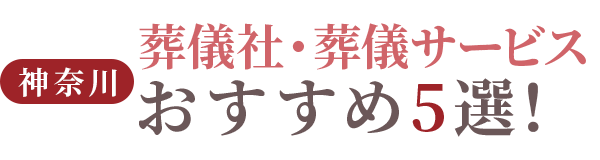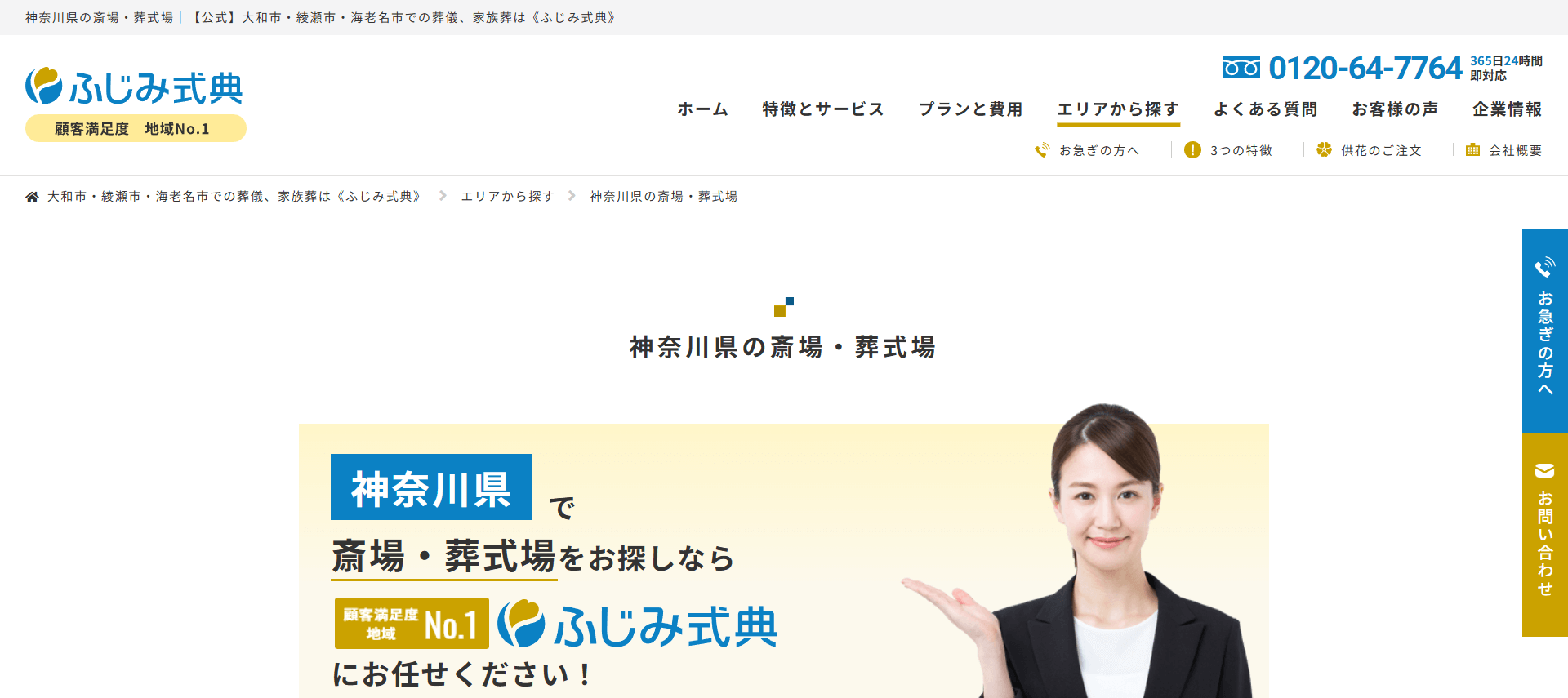葬儀費用は内容や規模によって大きく異なるため、相場や費用の内訳を知っておくことが重要です。どこに費用がかかり、どのように準備すれば安心できるのかを理解しておくと慌てずにすみます。また、補助金や給付金などの制度の活用も検討しましょう。この記事では、葬儀費用の基礎知識から相場、内訳までわかりやすく解説します。
葬儀費用の平均相場
葬儀を執り行う際に、もっとも気になるのが費用の問題です。一般的な葬儀費用の目安を知っておくことは、準備や心構えのうえでも重要です。葬儀費用の相場を確認しておきましょう。平均は約118万円
鎌倉新書が2024年に実施した「第6回お葬式に関する全国調査」によると、葬儀費用の全国平均は118.5万円でした。その内訳としては、葬儀一式にかかる基本料金が約75.7万円、会食やおもてなしにかかる飲食代が20.7万円、そして参列者への返礼品費用が22.0万円という構成になっています。減少傾向が続いている
直近の過去データを振り返ってみましょう。2022年に実施された第5回の調査では、葬儀費用の平均は110.7万円と、今回よりもさらに低い水準でした。そのときの内訳は、葬儀一式の基本料金が約67.8万円、飲食費が約20.1万円、返礼品が約22.8万円であり、小規模な葬儀が多く執り行われていたことが数字から読み取れます。こうした減少傾向の背景には、コロナ禍による人々の行動制限や、感染拡大防止のための葬儀の規模縮小があります。
実際、葬儀費用は2013年に202.9万円と高い水準を記録して以降、少しずつ下降線をたどってきました。2015年から2020年にかけては総額180万円前後で安定していましたが、2020年以降は新型コロナウイルスの流行をきっかけに一気に縮小し、2022年にはピーク時の約半分にまで減少したのです。
そして2024年の調査結果では、葬儀費用は再び118.5万円にまで回復しました。この数字は、2023年に新型コロナが「5類」に移行したことにより、参列者を迎える環境が整い、緊縮が続いた葬儀の形態にも変化が見られるようになったと考えられます。
2024年喉葬儀費用の平均が少々アップしている理由は、アフターコロナ期に入った現在の葬儀の実態が反映された結果であると考えられるのです。
家族葬が増加している
葬儀プランにも変化が見られるのが近年の特徴です。2024年の調査によれば、家族葬の割合は50.0%と、一般葬よりも多く選ばれています。加えて、通夜を省略して火葬のみを行う「直葬」「火葬式」など、さらに小規模なスタイルを選ぶ人も増えています。こうした傾向が、全体の費用を押し下げている大きな要因となっている可能性があります。
葬儀費用の内訳
葬儀にかかる費用は、大きく3つの要素に分けて考えることが重要です。ひとつは、葬儀そのものを執り行うための費用、次に参列者への接待に関する費用、そして宗教者へのお礼にあたる費用です。これらを合計した金額が「葬儀費用」となります。それぞれの内容や特徴を理解しておくことで、見積もりの際に不要な不安を抱えずに済むでしょう。
葬儀一式費用
葬儀の中心を占めるのが「葬儀一式費用」あるいは「葬儀本体費用」と呼ばれるものです。これは通夜や葬儀、告別式を執り行うために必要となる費用一式を指します。具体的には、セレモニーホールや斎場の使用料、祭壇や棺、遺影の準備にかかる費用、式を進行する司会者やスタッフの人件費などが含まれます。また、遺体の搬送に使用する寝台車や霊柩車の利用料もこの区分の費用です。
火葬にかかる料金は喪主が火葬場に直接支払う場合と、葬儀社が立て替える場合とがありますが、いずれにしても葬儀本体費用に含むケースが多いでしょう。請求書に「火葬費用」と記されている場合は、葬儀業者が立て替えた分の清算であることを理解しておくと安心です。
飲食接待費用
通夜振る舞いや精進落としなどの飲食にかかる費用と、香典返しといった返礼品にかかる費用を指します。葬儀社の見積もりにはあらかじめ含まれていることが多いのですが、参列者の人数に応じて変動するため、最終的な請求額は見積額と異なる場合が少なくありません。飲食費は人数によって大きく上下しますし、返礼品についても念のため多めに用意しておくのが一般的です。そのため、葬儀後に余った品物を葬儀社に返却し、実際に配った数で再精算することになります。
弔問に訪れる方の数は、事前に完全に予測できるものではないため、接待費用は事前に確定しづらいと理解しておくことが重要です。
宗教者に対する費用
お坊さんや神職に読経や戒名授与を依頼し、その謝礼として渡すのが「お布施」です。お布施は金額が明確に決まっているわけではなく、家庭ごとの考え方や菩提寺との関係性によって異なります。一般的には数万円から数十万円程度が目安とされていますが、近年は菩提寺とのつながりが希薄になってきたこともあり、「どのくらいが適切なのか分からない」と戸惑う方も増えています。その場合は、直接菩提寺に相談して差し支えありません。
また、お布施とは別に、お坊さんの移動にかかる「御車料」や、食事の代わりとして渡す「御膳料」を包むケースもあります。注意したいのは、こうした宗教者への費用は、基本的に葬儀社の請求書には含まれない点です。
喪主が直接宗教者へ渡すのが一般的であり、現金で手渡す場合が多いので、あらかじめ準備しておく必要があります。もし菩提寺や付き合いのある僧侶がいない場合には、全国どこでも定額で僧侶を派遣してくれるサービスを利用するという方法もあります。その際は金額が事前に明確に提示されるため、費用面での不安が少なくなるのがメリットです。
葬儀費用を左右する要因とは
基本的に葬儀の費用は、前述の3要素を加味して用意しておけば問題ありません。しかし、実際にはさまざまな要因によって、予定していた金額から変動するのが実情です。見積もりの段階では予想していなかった追加費用が発生し「思っていたよりも高額になってしまった」ということも少なくありません。なぜそのようなことが起こるのか、よくある要因を理解しておくことで、納得感のある葬儀ができるでしょう。
サービスの追加やグレードアップによる費用増
費用を増加させる要因のひとつが、オプションの利用料です。葬儀社が提示するプランには、基本的な内容が含まれています。しかし、それは最低限のサービスであり、満足いく葬式を求めると希望に沿わない場合があるので注意が必要です。たとえば、故人の体を洗い清める湯灌は、専用の設備やスタッフが必要であるため、標準プランに湯灌は含まれていないことが一般的です。また、遺体を長期にわたって保存するためのエンバーミング処置も同様であり、必要とする場合には別途料金が発生します。
さらに、棺や骨壺といった葬祭用品をより質の高いものに変更する場合にも、基本プラン料金に上乗せされます。こうした追加費用は、事前に確認していれば把握できるものなので、不明な点があれば早い段階で葬儀社に尋ねることが大切です。
参列者の人数に応じた費用増
次に大きく影響するのが、参列者の人数や状況に応じた費用です。飲食接待費や返礼品は、参列者が多ければ多いほど増える傾向があります。当初の想定よりも多くの方が弔問に訪れた場合、料理を追加したり返礼品を補充したりする必要が生じます。また、香典返しについても同様で、香典を受け取った方一人ひとりに返礼が必要となるため、想定外の出費となってしまうのです。
一方、葬儀社は豊富な経験をもとに余裕をもった数量を発注したり、大皿料理を準備して対応したりしますが、予測がむずかしい面もあり、最終的には人数次第で金額が大きく変動することがあります。参列者の数などは事前に完璧に把握できないため、プラン内でカバーできる人数などをしっかりと打ち合わせしておくことで、不必要な出費を減らせるでしょう。
搬送・保存状況による出費増
さらに注意したいのが、不測の事態に対応するための追加費用です。たとえば、遺体の保存に使用するドライアイスは、火葬までの日数や季節によって必要量が変わります。夏場や火葬の予約が混み合っている時期には、通常より多くのドライアイスを使用するため、その分の費用がかさみます。また、故人を病院から自宅や会場へ搬送する寝台車、会場から火葬場へ向かう霊柩車なども、移動距離によって金額が変動するので注意が必要です。
よって遠方への搬送を希望する場合には、事前に距離と費用を確認しておきましょう。こうした追加料金は、見積もりにすべてを反映することがむずかしいため、実際の請求金額と差が生じやすい部分です。
請求書に不明瞭な項目があればそのままにせず、担当者に確認しましょう。多くの場合、金額を確定できない理由が説明されるので、納得いくかたちで葬儀を進められるでしょう。
葬儀費用を抑える工夫
葬儀費用は決して小さな金額ではありません。突然の訃報に直面した際、思いがけない出費に戸惑う遺族も少なくなく、少しでも費用を抑えたいと考えるのは自然なことです。とはいえ、大切な人を送り出す儀式である以上、必要以上に節約して後悔が残ってしまうのは避けたいでしょう。ここでは、費用を必要以上にかけず、納得のいく葬儀を執り行うための工夫について解説します。
相見積もりを取る
葬儀費用を抑えるためにまず考えたいのは、複数の葬儀会社から見積もりを取って比較することです。同じように見える葬儀プランでも、含まれているサービスや葬祭用品の質、追加オプションの有無によって最終的な支払額は大きく変わります。複数社から見積もりを取った際には、金額だけに注目するのではなく「提示された金額でどこまでの内容が含まれているのか」という視点で検討するのが重要です。たとえば、基本プランに火葬料や返礼品が含まれているかどうかは葬儀社によって異なります。
見積書に記載された金額だけを見て判断するのではなく、飲食や返礼品、宗教者へのお布施なども含めた全体予算を想定しながら比較すると、より正確に判断できるでしょう。さらに、見積もりを提示するまでの接客対応、レスポンスの迅速さなどにも気を配り、誠実に対応できるかも検討しましょう。
利用者にていねいに対応できるかは、葬儀のクオリティを図るうえで重要な指標です。もしぞんざいに対応されたり、レスポンスが遅かったりする葬儀会社は、期待する葬儀サービスを受けられない可能性があるので避けることをおすすめします。もし時間に余裕があるなら、生前のうちに複数社の見積もりを取り、内容を吟味しておくと安心です。
葬儀プランを見直す
葬儀費用を抑えるためには、葬儀の形式や規模を見直すことも効果的です。一般葬のように多くの参列者を招く形式は、比例して費用も多くかかります。一方で、最近では家族葬や一日葬といった小規模な葬儀を選ぶ方も増えており、さらに通夜を執り行わず火葬だけですませる直葬・火葬式プランを選択すると、もっとも費用を抑えられます。故人の交友関係や年齢によって参列者の数は異なるので、本人が「できるだけ簡素に」と望んでいたケースでは検討の余地があるでしょう。葬儀プランの選択傾向は、そのときの社会情勢により異なる傾向を見せ、近年ではコロナ禍の影響が残り、一時期よりは縮小される傾向にあります。
よって無理して高価なプランを選択したり、多くの参列者を招いたりする必要はありません。家族の希望と故人の意思を踏まえて、適切な規模を検討することで、無理のない葬儀を執り行えるでしょう。
飲食代や葬祭用品を見直す
葬儀費用を調整しやすい項目として、飲食代や葬祭用品があります。通夜振る舞いや精進落としに出す料理は、品数やコースの内容によって金額が大きく変わり、参列者に失礼のない範囲で、必要十分な内容に絞るだけでも負担を軽減できます。また、棺や骨壺、祭壇や生花といった葬祭用品は、グレードの高いものを選ぶとすぐに数万円単位で増額されるので、品質を重視する部分と、価格を優先できる部分を見極め、適切に調整するとよいでしょう。
香典でまかなう
香典を葬儀費用に充てるのも、負担を軽減するのに効果的です。そもそも香典は、故人の遺族を支える意味をもつものであり、受け取った香典を葬儀費用に充てることは決して不自然ではなく、むしろ参列者全員で故人を見送る行為のあらわれといえるでしょう。香典の総額は参列者数や関係性によって大きく変わりますが、一般的には費用全体の3分の1から半分程度をまかなえるケースが多いとされています。葬儀負担を遺族だけで背負わず、社会全体で支え合う仕組みとして香典が存在することを理解しておくと、気持ちも楽になるでしょう。
葬儀保険に加入する
訃報は突然発生してしまうものです。しかし、事前に準備できる方法として葬儀保険に加入しておくという選択肢もあります。これは死亡時に葬儀費用をまかなうための保険で、終活保険や死亡保険と呼ばれることもあります。葬儀保険は、月々の保険料を支払い、万が一のときにまとまった金額を受け取れる仕組みです。
加入には事前の手続きが必要で、故人が亡くなった後では加入できませんが、もし備えられるのであれば、遺族に経済的な負担をかけずに済む有効な方法といえます。
僧侶手配サービスを活用する
仏式葬儀でお布施にかかる費用を抑える工夫として、僧侶手配サービスの利用も有効です。本来は、菩提寺の住職に依頼するのが一般的ですが、お布施の金額が高額で負担が大きく、なにより近年では菩提寺がない方も多いです。その際には、全国一律の料金で僧侶を紹介してもらえる僧侶手配サービスを活用しましょう。依頼したからといって檀家になる必要はなく、葬儀の一度きりの利用も可能です。
菩提寺との縁が薄い家庭にとっては、安心して利用できる選択肢となるでしょう。
葬儀の見積もりを確認する際の注意点
訃報は突然訪れることが多く、時間的にも精神的にも余裕がない中で多くの判断を迫られます。そのため、見積もりを十分に確認しないまま契約すると、後から「想定より費用がかさんでしまった」「思っていた内容と違った」となりかねません。ここでは、葬儀の見積もりを確認する際に押さえておきたい注意点を解説します。
内容をしっかり確認する
まず大切なのは、提示された金額だけに注目せず、見積もりの中身をしっかりと精査することです。近年では、格安をうたった葬儀プランも数多く見られますが、その内容をよく確認すると、火葬料や搬送料、ドライアイスの追加など基本的な費用が含まれていないケースがあります。総額10万円を切る一見お得なプランであっても、最低限の内容しか入っておらず、必要に応じてオプションを追加すると一般的な葬儀と同等、あるいはそれ以上の費用になることもめずらしくありません。さらに注意すべきは、広告や宣伝の表現を鵜呑みにしないことです。
たとえば「追加料金不要」と大きく打ち出していても、実際には別途費用を請求されたという事例があり、消費者庁から措置命令を受けた葬儀社も存在します。不自然に低価格を強調している場合は、必要な項目が含まれていない可能性が高いため、見積書に記載された項目の内容や数量、追加料金の有無をしっかりと確認し、どの範囲までカバーされているのかを把握して契約するのが大切です。
金額を重視するあまり個々の説明を省略してしまうと、サービスの内容を十分に把握できず、後から「思っていた式と違う」と不満に感じることがあります。反対に、担当者としっかり打ち合わせをして、納得したうえで葬儀を進めたケースでは、費用に関わらず満足度が高い傾向にあります。不明点があれば遠慮せず質問し、契約前にできるだけ疑問を解消しておくことが望ましいです。
信頼できる葬儀会社か見極める
見積もりを受け取って契約するまでの間に、信頼できる葬儀会社かどうかを見極めましょう。その方法のひとつが、利用者の感想や口コミを確認することです。公式ホームページではよい面が強調されがちですが、実際に利用した人の声には、現場での対応や担当者の人柄、式の進行に対する感想などが反映されています。もちろん口コミには個人の主観も含まれますが、複数の意見を見比べれば、その葬儀会社の特徴や傾向を把握しやすくなるでしょう。
また、葬儀会社の中には、費用を抑えるために経験の浅いスタッフに任せたり、儀式を効率的に進めすぎたりして遺族が不満に感じるケースもあります。一方で、限られた予算の中でも誠実に対応し、最後まで心を尽くす葬儀会社も少なくありません。
契約するまでのコミュニケーションやレスポンスなどから、遺族に対する姿勢や誠意を見極めることが大切です。担当者とのやり取りや口コミの確認を重ねることで、納得のいく葬儀につなげられます。後悔しないためにも、見積もりの段階では慎重に検討するよう心がけましょう。
葬儀で申請できる補助金・給付金
葬儀費用は決して小さな負担ではなく、遺族にとって大きな経済的な悩みとなりがちです。しかし所定の手続きをすれば、一定の補助金や給付金を受け取れる制度が多く存在します。健康保険や共済組合、国民健康保険など、加入している保険の種類によって金額、申請方法は異なるので、あらかじめ確認しておくことが大切です。
埋葬料または埋葬費
健康保険または共済組合に加入している方が亡くなった場合、遺族は「埋葬料」または「埋葬費」を受け取れる可能性があります。埋葬料は被保険者が死亡したときに支給され、申請期限は死亡の翌日から2年以内です。一方埋葬費は、実際に葬儀を実施した人に支給され、こちらも埋葬翌日から2年以内に申請する必要があります。法定給付額は5万円と定められており、葬儀費用の一部をまかなえます。
葬祭費
国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」と呼ばれる給付金があります。こちらは全国一律ではなく、申請する自治体によって1〜7万円の範囲で支給額が異なります。申請期限は、葬儀を実施した日の翌日から2年以内と定められています。なお自治体によっては、直葬や火葬形式を葬儀とみなさず、葬祭費の対象外とする場合があるため、事前に確認しておきましょう。
葬祭扶助
経済的に困難な場合に利用できるのが「葬祭扶助」です。これは生活保護を受給している方が利用できる制度であり、生活保護法に基づいて最低限のお別れを可能にするもので、遺体の検案や搬送、火葬や埋葬、納骨といった必要最低限の範囲を対象としています。祭壇や僧侶による読経など、火葬以外の部分には適用されません。支給額は自治体や年度によって異なりますが、目安として最大20万円前後です。
費用は福祉事務所から直接葬儀社へ支払われ、遺族の手元に現金が渡ることはありません。また、葬儀前に申請する必要があり、後からでは認められないケースが多いため注意が必要です。
互助会制度・会員制度
補助金や給付金以外で葬儀費用を軽減する方法として、葬儀社が提供する「互助会制度」や「会員制度」があります。互助会制度は経済産業省の認可を受けた葬儀社が運営しており、毎月一定額を前払いで積み立てる仕組みです。将来の葬儀や結婚式に備える制度で、積み立てた分は葬儀費用の補填にあてられます。さらに会員は提携施設やサービスを通常より安く利用できるなどの特典もあります。
ただし、利用できる葬儀社やプランが限定されること、解約時に手数料がかかることなどデメリットもあるため、加入前によく確認しておく必要があります。一方、会員制度は互助会のように積み立てする必要がなく、一度入会金を支払えば会員特典を受けられる仕組みです。
特典の内容は葬儀社ごとに異なりますが、式場使用料や祭壇費用の割引、葬祭用品の優待価格などが一般的です。互助会に比べて自由度が高く、費用の負担も軽いため、特定の葬儀社を利用したいと決めている場合には有効な選択肢といえるでしょう。